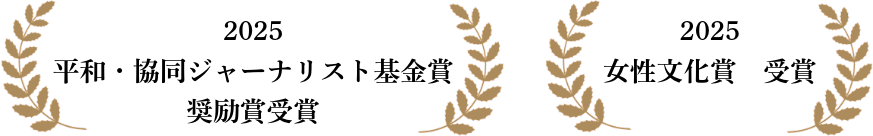今から10年ほど前、敗戦直後の満洲で起きた性暴力の実態を佐藤ハルエ、安江善子が自ら告白した。当時、ソ連軍に差し出された女性は15人。数えで18歳以上の未婚女性が犠牲となった。
今はどこにもない国、満洲国。岐阜県にある白川町黒川からも佐藤ハルエ、安江善子を含む650人余りの人々が黒川開拓団として海を渡り、丸5年その国で生活を送った。


性接待の犠牲を払いながらも敗戦から1年、黒川開拓団の人々は帰国した。しかし、帰国した女性たちを待ち受けていたのは差別と偏見の目。二重の苦しみに追い込まれ佐藤ハルエは、故郷を離れるしかなく、未開の地・ひるがのをゼロから開墾し借金をして酪農を始めた。安江玲子は黒川を離れ東京に。夜も眠れない毎日が続いた。水野たづは、決して口外することはなかった。それぞれが思いを抱え、それでもこの思いを口にすることなく、時に性接待の犠牲にあった女性たちのみで集まり涙をこぼした。そんな日々が続いた中、2013年満蒙開拓記念館で行われた「語り部の会」で佐藤ハルエと安江善子が、性暴力にあったことを公の場で明かした。彼女たちの勇気ある告白に、今度は、世代を超えて女性たちが連帯した。彼女たちの犠牲を史実として残す。戦後70余年、黒川の鎮守の森に碑文が建てられ、その歴史が公に刻まれることとなった。
戦後80年の時を経て、女性たちに大きな変化をもたらした。過去に向き合うこと、それは尊厳の回復にもつながることだった。